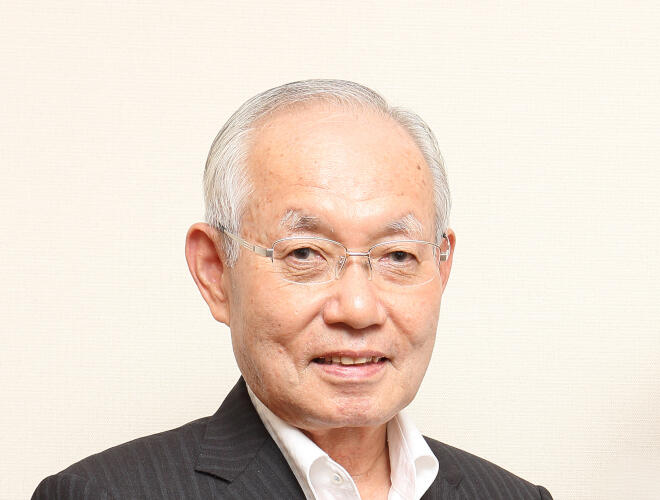
2025/11/06
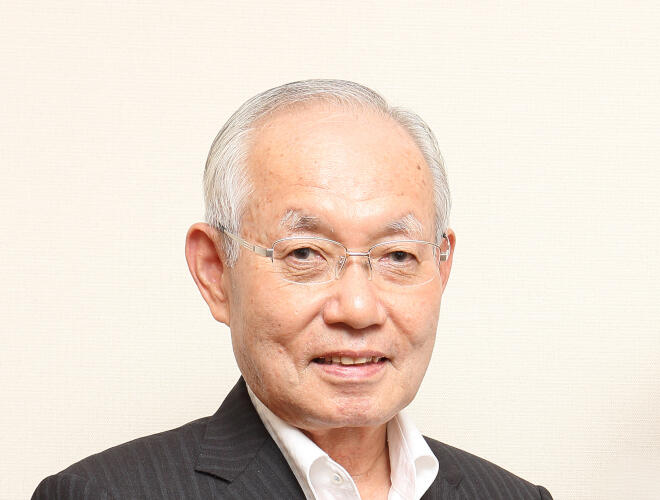
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
今年2025年は戦後80年ということで、忌まわしい戦争の記憶を想起して、悲惨な空襲体験や、許しがたい広島・長崎の原爆被爆経験が語られ、この悲劇を二度と繰り返さないための誓いが、多くの人々が参加して各地でなされた。
もう亡くなってしまったが、筆者の親類も「無差別に機銃掃射するパイロットの顔が見えるほどの低空で戦闘機が飛んできた」と恐怖の経験を語ったことがあった。
とんでもないほどの数の無辜の人々が無差別に空襲や原爆で殺戮されていったのだが、こんな体験が再現されてはならないと心から思う一方で、なぜこのようなことが起きてしまったのかへの思考や研究が不足しているのではないかと考えてしまうのだ。
「悲しい出来事は二度とあってはならない」と叫ぶだけで、二度と起こらないと考えるのは、かなり甘いという思いなのである。
議員というより作家として評価したい猪瀬直樹氏に「昭和16年夏の敗戦」という好著がある。1941年に総理直属の総力戦研究所が平均年齢33歳の模擬内閣を構成して、対米戦争のシミュレーションを行ったが、何度繰り返しても結論は「日本必敗」となったというのである。もちろん上層部はこれを完全に無視したのだ。
現在の政治もほとんどこれに近いと思うのだが、「これは私の責任で決めたことです」と名乗る政治家はほとんどいないという日本国事情の恐ろしさなのだ。上記のようなシミュレーションがあっても、「もう開戦への流れは止められない」と判断を放棄して状況に身を任せるという「無責任という日本国事情」である。
対米戦争開戦時ころのGDPの格差は、アメリカは日本の5倍以上、自動車の生産能力は100倍もの格差があり、これでは飛行機などを動員して戦う近代戦で互角の勝負などできるわけがない。おまけに戦争用素材の製作能力や品質管理能力なども大きく劣後していた。
というのは次のようなエピソードがあるからなのだ。横浜駅のすぐ近くに「原鉄道模型博物館」がある。ノートなどで有名なコクヨに勤務していた原信太郎氏が、コツコツと鉄道模型製作に挑み、その精度と製作量が他を圧倒するスケールであったから、それを三井不動産のビル内に博物館を設けて展示しているものだ。
ここで紹介したいのは、この博物館のことではなく、鉄道模型を作った原さんのエピソードだ。原さんは、現在の東京科学大学(少し前までは東京工業大学・戦前は東京職工学校)の出身なのだが、戦前にこの大学に初めて自動車部を作ったというのだ。
その時にフォードとトヨタ(もちろん当時の)のエンジンを解体して見てみたのだが、原さんは即座に「これでは戦争に勝てるわけがない」と語ったというのだ。彼のこの発言は軍部の知るところとなり、エリート校の大学生だったのに二等兵で招集されたといわれる。当然、自動車だけではなく戦車のエンジンも大きく劣後していたに違いない。
というのも、馬力の出ないエンジンしか装備できていないから、当時の写真でも明らかだが、ドイツのタイガーⅡ戦車に比べるとおもちゃのような大きさで、敵の攻撃を正面で受けるための戦車装甲鉄板も向こうは250㎜という厚さなのに、日本のは高々25㎜という薄さだった。エンジンが貧弱だから重くなると走れないのだ。
われわれは具体の事実に基づいた議論や思考の組み立てができない国民ではないかと考え込んでしまうのだが、もちろんそれがすべてであるわけもない。そんなことでは、現在のトヨタ自動車もNTTも三菱重工業も成り立つはずもなく、正確な事実と隙間のない論理構成力があるから、今日の日本企業は他国に勝る競争力を獲得できているのだが・・。
シミュレーションを繰り返しても対米戦争に勝利できるという解はまったく得られなかったという事実。装甲を薄くして搭乗員の命を守ることもできない戦車しか作れなかったというレベルの工業力。
なるほどゼロ戦は優れた戦闘機であったが、本来搭乗員を守るための背中側に装備すべき防弾装置(鉛板など)は機体重量が重くなりすぎて飛行性能が落ちるからと簡易化してしまったのだ。それもあって開戦当初には多くいた訓練豊富な優秀パイロットは戦闘のたびにみるみる損耗して、戦争末期には素人のようなパイロットばかりとなってしまった。
二度と繰り返してはならない失敗とはこのようなことであったと考えるのだ。ほぼ人の一生にあたる80年を経て「過ちを繰り返すな」と叫ぶのだが、この反省を踏まえて軍事強国を捨てて、経済大国への道を歩んで豊かな生活を手に入れるための方策に邁進してきたはずなのに、何もかもがうまく回らない無策の国となった。
それが日本の経済力を大きくそいでGDPの世界シェアを井戸の釣瓶が落ちていくように落としてきたし、著しい国民生活の貧困化と経済や科学的研究の競争力の毀損を生んでしまった。世界の約18%を占めていたGDPは今や4%というありさまだ。
スイスのIMDが発表する世界競争力(政府のビヘイビアなどが評価の対象)の世界順位は、かつて1位を独占する勢いだったのに、直近では35位(2025年・韓国は27位)という状況だ。いま叫ぶべきことは、「二度と銃を持たない」もいいのだが、「理性的に物事を考えることのできる、国民が豊かで競争力のある国の実現」なのではないか。
これを忘れて日本の政治やオールドメディアは、高橋洋一氏の言う「財源至上主義」に陥っており、何か政策的達成を図ろうとすると「財源はどこにある」という言葉ばかりが跋扈して、「実現すべき政策」がどこかに飛んでいる。減税に財源など不要で、必要なのは経済成長なのだが、「競争力が世界35位で成長できるのか」と叫ぶ政治家は皆無なのだ。
猪瀬直樹氏が紹介した研究所報告でも対米戦争は必敗予想だったが、それでも戦争に向かったのは世論が推したことが大きい。戦後、「なぜ戦争に走ったのか」という議論になったときにある右翼団体のトップが「新聞がなければ戦争にはならなかった」と述べたことがある。
今年の80年の反省でまったく欠けていたのが、メディアが開戦に果たした役割である。
(月刊『時評』2025年10月号掲載)