
2025/11/10
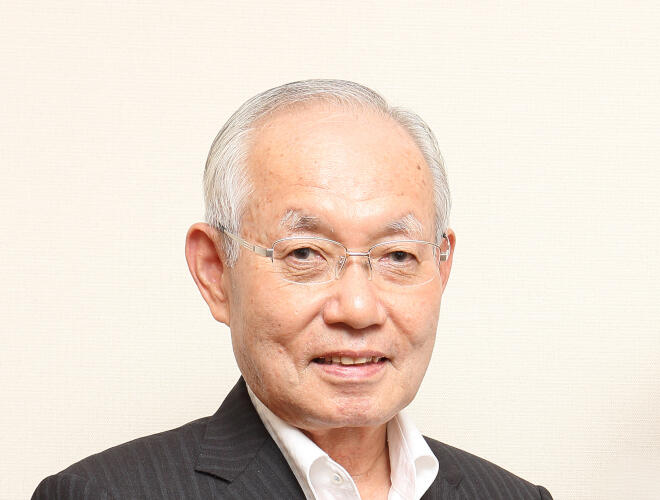
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
経済という言葉は、「経世済民(世を収め民の苦しみを救うこと)」を略したものだと言われている。とすると、経済学者は国民が窮乏化していく際には、救済策を研究し、政治に提案しなければならない責務を負っていると考えなければならないだろう。
特に国立大学の経済学者は、国費で研究しているのだから、私立の経済学者よりもより多くの、より有効な「民を救う」政策を国に提案する責務を負っていると考える。
ところが、現実は全くそうはなっていないのだ。日本人という「民」はとんでもない経済的苦しみに遭遇しているのだが、その救済策が「経済学者から全く提案されない」のである。
何度も示すようだが、以下に再掲するのは経済学者の怠慢を再確認するためである。つまり、日本国民は恐るべき早さで窮乏化してきたし、それは今なお進行中である。
世帯所得
1995年 660万円
2021年 545万円
(115万円ダウン)
年収中央値
1995年 505万円
2022年 374万円
(131万円ダウン)
世帯可処分所得(森永卓郎氏による)
1998年 384万円
2021年 366万円
(18万円ダウン)
生活保護世帯
1995年 14万世帯
2024年 165万世帯
(151万世帯増)
海外からも、日本経済の停滞ぶりについて、厳しい批判が相次いでいる。カナダの経済学の世界では、「国民は勤勉で、怠惰でもスキルが低いわけでもないが、国民の貧困化が進行しているのは世界に例を見ない政策ミスによるのである」と議論されているという。
西欧では、「日本化は避けるべき」といわれているというし、東南アジアからは「日本にアジアのリーダーになって欲しいと期待していたが、現在は急速に没落しているが、大丈夫だろうか」という声が出ている。
こうした声が出るように、海外の人に心配されるほどに日本の経済的地位も急速に低下し、もはや経済大国など夢の夢というのが現実なのだ。アメリカを1・0としたときの、日本の一人当りGDPを示すと「1993年は1・6だったが、2023年には0・4となった」という報告がある。
G7各国の名目賃金の推移を見ても、この30年ほどで、全く伸びを示していないのが唯一日本で、他のG7国は、2倍から3倍と伸びている。
にもかかわらず、政治の世界では国民をさらに貧困化させる増税議論に終始している。憲法前文には「(政治行為の結果)その福利は国民がこれを享受する」とあるから憲法違反の政治が続いているのだが、政治家は何の反省も示すどころか貧困化の促進に精を出している。この状況に責任のある経済学者から何か政治に対して声を出したのだろうか。皆無ではないか。それでは日本の経済学者は不要なのではないか。政策ミスを正すべき責任を感じないのか。
実は、国民の貧困化などに何の関心もないのが経済学者たちなのだ。その証拠が、東日本大震災時の彼らの行動である。なんと有力経済学者たちは、この地震からの復興のために増税を主張したのだ。2011年5月(この時、すでに国民の貧困化は進行していたのだ)に「復興費用は全国民が薄く広く負担すべき」との声明をしたが、これに名を連ねていたのは、
伊藤隆敏 伊藤元重 土井丈朗 深尾光洋 八代尚宏 吉川洋 大竹文雄 塩路悦朗 その他(条件付き賛同者)
などの経済学のそうそうたるメンバーで、他からの異論を許さないという陣容である。この声明は財政再建の主張にまことに迎合的だが、ではなぜこの地震より被害額の大きかった阪神淡路大震災では経済学者たちは増税の主張をしなかったのか。以前の大災害では増税など主張しなかったが、今回の災害は以前の災害と何が違うのか。つまり、これは誰かの指示があったのではないか。経済学者たちは、常に誰かからの指示待ちなのではないか。
わが国が経験した最大の災害は関東大震災時だが、外国から借り入れる外債は出したけれども復興増税などしてはいない。それでも昭和通り、八重洲通り、隅田公園など莫大な復興資産を残している。将来の資産となる復興に国債を充てるのは常識ではないか。
経済評論家の中野剛志氏は、経済学ノーベル賞受賞者のポール・ローマーの説いた「経済学者の七つの特徴」を紹介している。
1 途方もない自信
2 異常に一枚岩の共同体
3 宗教団体か政党のような同じグループとの一体感
4 他分野の専門家から隔絶された強烈な内輪意識
5 他グループの専門家の思想、意見、業績に対する無視と無関心
6 証拠を楽観的に解釈し、結果に対する大仰あるいは不完全な言明を信じ、理論が間違っているかもしれないという可能性を無視する傾向
7 研究プログラムに伴うはずのリスクの程度に対する評価の欠如
まさに日本の経済学者たちの行動を読んで作ったかのような整理である。
多くの大学などに経済学者といわれる方々が大勢いるが、上記に示した国民の貧困化の防止に対して、誰も有効な施策を提案したことがないのだ。
東京財団が2023年に発表した経済学者282人へのアンケート調査では、日本経済の将来的な経済成長の可能性について「成長は困難」が50%で、「日本の財政政策は効果を発揮したか」には半数以上が「あまり発揮していない」と答え、自己通信簿を示しているが、自分たちの責任を棚に上げた評論家の域に安住していることを示す調査結果だ。
国民を豊かにする政策を何も提言できない経済学者など、存在する理由があるのだろうか。
(月刊『時評』2025年4月号掲載)