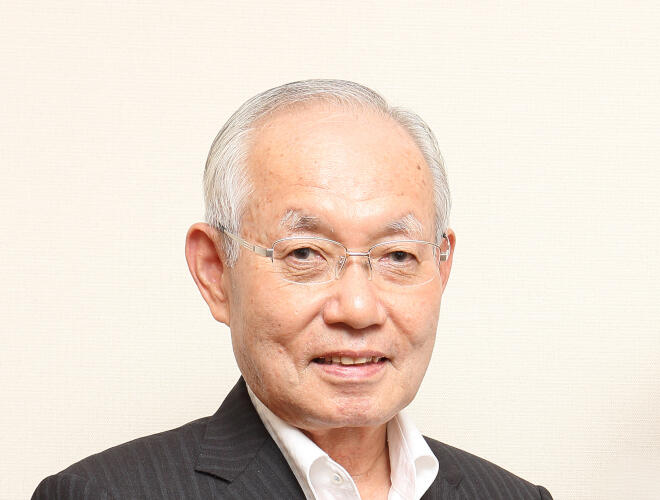
2026/01/06

今年1月28日午前9時50分ごろ、埼玉県八潮市で道路が陥没し、トラック1台が中に転落した。
当初はドライバーの声が聞こえたというが、結局、未だに無事に救出されるには至らないという痛ましい結果となった。
道路の下を通る下水管が破損したことが原因であるという。
この道路陥没事故を契機として、多くの地方公共団体では、下水道の緊急点検を実施するなど、対応に追われた。
水道管路の法定耐用年数は40年、物理的な耐用年数も50年程度と言われているが、わが国の上下水道管路の相当な部分が高度経済成長期に整備され、こうした耐用年数を超えているという。
わが国の全管路延長約74万キロメートルのうち、およそ4分の1が法定耐用年数を超えて老朽化しており、その割合は年々増加しているという試算もある。
こうした状況にあって、漏水・破損事故は年間2万件程度発生しているとも言われており、まさに上下水道の老朽化対策は喫緊の課題となっている。
水道管路に限らず、交通インフラに関わる道路、橋、トンネル等々や、近時の天候の激烈化に対応すべき排水溝や融雪設備などのさまざまなインフラは、高度経済成長期以降に急速に整備された部分が多い一方、その後のメンテナンスに関する見通しと対応が必ずしも十分ではなく、老朽化対策が待ったなしとなっている。
しかし、他方で、わが国の人口減少が見込まれる状況にあって、こうしたインフラに投資することの効果が疑問視される部分もあり、また国も地方も財政が厳しくなる中、十分なインフラ投資が行われているとは言えないのが実情だ。
こうしたハード面でのインフラだけではなく、教育や医療といったソフトインフラに目を転じても、状況は厳しい。
イギリスの有力な高等教育専門誌「THE Times Higher Education」が昨年10月に発表した「世界大学ランキング2025」では(「教育」「研究環境」「研究の質」「産業界」「国際性」の5分野についてスコア算出)、米国、英国、中国の大学が上位に並ぶ中、日本で最高位となる東京大学が第28位、続く京都大学が第55位となっている。
医療システムも、コロナ禍にあっても医療従事者の献身的プロフェッショナリズムのおかげで瓦解はしなかったとはいえ、インフラとしての脆弱性を示したことは記憶に新しい。
しかし、だからといって、その後に医療インフラが抜本的に強化されたとは聞かない。
こうしたハード、ソフトのインフラの劣化状況は、日本という国が「盛りを過ぎた国」となりつつあることを象徴しているようにも見える。
高度なインフラを整備して「すべての道はローマに通ず」と言わしめたあのローマ帝国も、盛りを過ぎた時代にはインフラの劣化は否定できなかった。
インフラの劣化が国家的衰亡の「結果」として起こっているという危機感を持つことは、歴史を振り返る限り、あながち誤ってはいないだろう。
他方で、こうしたインフラの劣化は、国家の衰亡を早める「原因」ともなることを見逃してはならない。
そもそもインフラとは、私たちの生活や経済活動を支えるために必要な共通利用を前提とする施設・設備やソフトなシステムである。
こうしたインフラが劣化すれば、私たちの生活が不安定化して安全・安心が損なわれるとともに、経済活動が非効率化していくことは当然であろう。
いま、日本は、インフラ劣化と国家衰亡の悪循環に陥るかどうかの瀬戸際にあるといっていい。
しかし、希望もある。
この危機的状況を奇貨として、賢明な政策選択ができるならば、悪循環を逆転させて国勢を向上させることもできるのではないか。
国も地方も財政が厳しい中、ポピュリズム的なバラマキ政策に資金を投じるのではなく、公共の役割を再確認して、インフラを「賢く」再構築・再整備していくことを推進すべきである。
もちろん、インフラ整備のためとして公共工事のバラマキを行うような愚かなことは許されない。
そもそもインフラとは、共通利用によって効率化を図るものであって、人々が集住する都市部でこそ必要性が高いものだ。
日本全国どこでも同程度のインフラ整備を求めることは賢明ではない。
あるいは、人々の集住を進めることとインフラ整備は政策の両輪として同時に進めるべきかもしれない。
ある意味で厳しいかもしれないが、そうした政策を掲げて国民に提示し、道筋をつけていくことこそ、責任ある政治・行政というものであろう。
逆に、実現できないバラ色の夢を語ることは、うそになる。あえてうそを誠にしようと進めば、それは悲劇になる。
そこに悪気はないのかもしれないが、そうしたうそに付き合う余裕はこの国にはもはやない。
(月刊『時評』2025年4月号掲載)