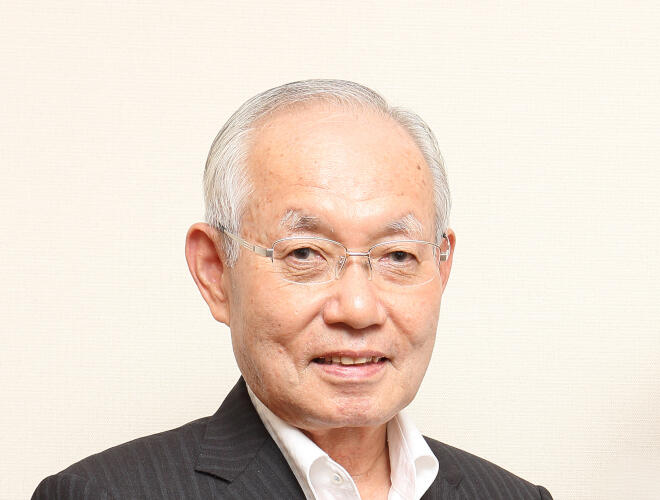
2026/01/06

「民度」という言葉がある。
一般的には、特定の国や地域に住む人々の知的水準、教育水準、文化水準、行動様式、マナーなどの平均的な成熟度の程度を指す言葉とされる。
程度を指すからには、ややもすると、他国との比較において「民度が高い」「民度が低い」というと、差別的表現とされてしまう言葉ではある。
実際、例えば、2020年のコロナ禍にあって、麻生太郎副総理兼財務相(当時)は、国会において「うちの国は国民の民度のレベルが違う」ことをコロナによる死亡者が少ない理由として指摘して、一部から「差別的だ」という批判を受けた。
しかし、異なる結果があるならば、その原因となる何かに相違があると考えるのは当然の思考経路であり、考え得る相違点の指摘自体が差別的だという批判は議論のモダリティ(様相、手順)としては、いささか疑問がある。
むしろ、そうしたある種の「言葉狩り」によって、議論自体が封殺されることは、民主主義を廃退させる要因となる恐れさえあるだろう。
あえて「民度」という言葉を持ち出したゆえんは以上のとおりであるが、近時、わが国の「民度」が低下しているのではないかという趣旨の指摘が散見される。
ネット上を検索すれば、日本の「民度」低下に関する多くの発信を容易に見ることができる。
例えば、著名なミュージシャンであるGACKTは、大阪・関西万博で警備員が来場者に土下座をした件に関連して「この20年で、日本の民度が落ちていることが悲しい。カスハラなんてのは民度の低下を表している代表例だろ?」とSNSで発信して話題となった。
いま、虚心坦懐に日本の状況を見れば、そうした「民度」の低下と政治のポピュリズム化がスパイラル的に進行していく姿を私たちは目撃しているのではないか。
その先に待ち受けているのは、悲惨な未来でしかないことを、古代ローマの「パンとサーカス」に象徴されるポピュリズム政治以来の多くの歴史が教えている。
今夏の参議院選挙を控えて、与野党ともにさまざまな政策提言(公約)を議論しているが、減税や給付金など、一時的に有権者受けする議論も少なくない。
確かに、かつて大野伴睦が語ったように「サルは木から落ちてもサルだが、代議士が落ちればただの人」とはいうものの、落ちないためには「何でもあり」ではないだろう。
そうした中、石破総理がFNNのインタビューにおいて、夏の参院選に向けて「未来に責任を持つということだ。選挙の時にその場でウケるような政策は党の議席増にはつながっても、本当に次の時代のためになるのかということだ」と述べたことは注目に値する。
選挙に向けて、石破総理のこの真摯な思いが貫徹されることを期待したい。
民主主義における選挙は、統治の正当性の根拠だが、残念ながら、いろいろな陥穽があると指摘されている。
その中でも、選挙には「未来世代が参加しない」という点は、現世代が未来への責任をどれだけ引き受けるかという切実な問いに直結する。
石破総理の発言は、この切実な問いに自覚的で、正面から向き合おうとする政治からの真摯な発言に他ならない。
また、石破総理のみならず、与野党の心ある政治家からは、時として選挙対策という現実との間で煩悶しつつも、同様の趣旨の発言が聞かれる。
そうした「未来への責任を果たそう」という政治からの呼び掛けに、いかに国民が応えるのか、いかに選挙において意思表示をするのか、という点に、私たちの「民度」が示されるのではないか。
かの松下幸之助は「民主主義国家においては、国民はその程度に応じた政府しか持ちえない」と指摘し続けた。
民主主義においては、国政に限らず、地方自治においても、この指摘は正しい。
私たちが、目先の利得にのみとらわれて、朝三暮四的な議論に乗せられて、あるいはフェイク情報を信じて、未来への責任を忘れてしまう程度の「民度」であれば、日本の衰亡は決定的であろう。
近く行われる選挙において本質的に問われるのは、候補者の政治家としての資質や実績ではなく、ましてや候補者の知名度や人気でもない。
むしろ、本質的に問われるのは、私たち自身の「民度」なのである。
サミュエル・スマイルズが喝破したとおり「一国の政治は、国民を映し出す鏡に過ぎない」(『自助論』)。
来るべき選挙において示される私たちの「民度」によって、私たちの未来が、日本の未来が指し示されることになる。
「民度」の低下と政治のポピュリズム化のスパイラル的な進行を反転させることは容易ではないが、不可能ではないはずだ。
日本の衰亡を押しとどめ、未来に向けて再興していくチャンスとして、迫りくる選挙を迎えたい。
(月刊『時評』2025年6月号掲載)