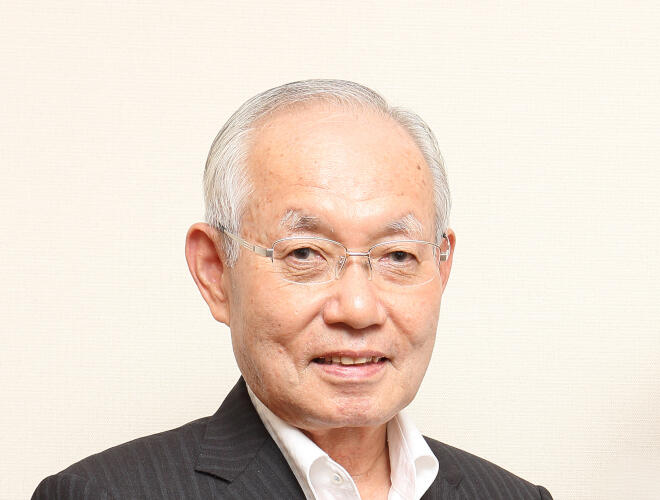
2026/01/06
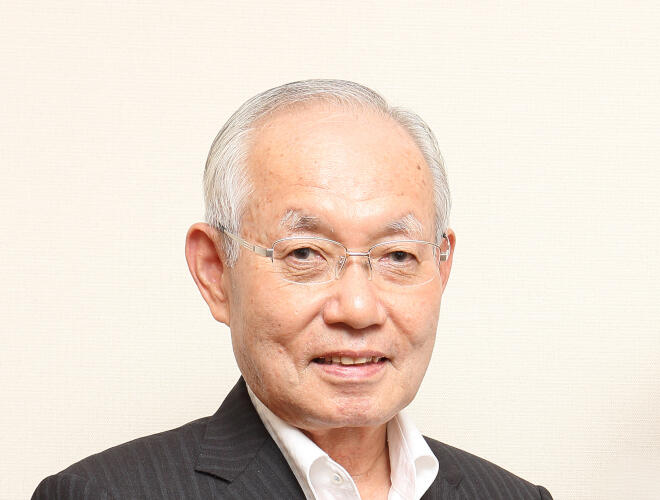
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
日本のオールドメディアはいまだに政治家のパーティー券問題などは報道するが、国民の貧困化についての現状の確認や、貧困化からの脱出についての政策議論など全く報道できていないという体たらくに落ち込んでいる。
ここでは何度も紹介している国民の貧困化の実態がまったく「国民に知らされていない」から、国民が「今の政治のままでいいのか」と気づく機会もないという状態だ。何度も紹介するのもなんだけれども、やはり基本の認識として示さざるを得ないのは世帯収入の推移だ。
世帯収入の推移
1995年 660万円
2021年 545万円
ここまで減ってきたという事実と、このように哀れな状態になっていく国民は、先進G7国では日本人だけだという事実を国民が認識すれば、今のわが国の情けないを通り越すレベルの政治世界における議論を、これは先の大戦の大敗北並みの惨状であると理解できることだろう。
OECDがまとめた「G7各国の賃金推移」を見てみよう。
1991年を100として2020年の名目賃金は
日本 111・4
イギリス 265・6
アメリカ 278・7
カナダ 227・6
ドイツ 216・0
フランス 194・9
イタリア 179・2
となっており、情けなくもG7国で日本人の名目賃金だけが伸びていないことがわかる。
では、物価変動を加味した実質賃金で見てみると
日本 103・1
イギリス 144・4
アメリカ 146・7
カナダ 137・6
ドイツ 133・7
フランス 129・6
イタリア 96・3
イタリアはどういうわけか、名目賃金は大きく伸びていたのに大きな物価上昇により実質賃金はひどいことになっている。しかし、この例外を除くと他の諸国は日本よりはるかにといえるほどに実質賃金も伸びている。
こうした情報も、G7各国の実態比較もオールドメディアからまず紹介されることはないのだ。さらに何度も述べなければならないのは、この実態に対して経済学者からの反省や、この状況を打開するための政策提言などが皆無というのも、惨状といえるだろう。
「経世済民=世を収め、民の苦しみを救うこと」(=経済という用語のルーツ)は日本には存在しないのだ。大学の経済学部の先生たちは、いったい毎日何をしているのだろう。
昔を振り返っても日本政治は「現状を否定し、改革を志向する」ことばかりをやってきた。
1961年 第一次臨時行政調査会 佐藤喜一郎会長
1981年 第二次臨時行政調査会 土光敏夫会長
1983年 第一次臨時行政改革推進審議会 土光敏夫会長
1987年 第二次臨時行政改革推進審議会 大槻文平会長
1990年 第三次臨時行政改革推進審議会 鈴木永二会長
1994年 行政改革委員会 飯田庸太郎会長
1996年 行政改革会議 橋本龍太郎会長
1998年 中央省庁等改革基本法
2001年 上記法律に基く中央省庁再編 一府十二省庁に再編
この2001年の省庁改革・再編には大きな問題が隠されていた。
橋本龍太郎内閣は1996年に行政改革会議を設け省庁再編へと走り出した。省庁の縦割りを排し、行政の効率化を図るとしたこの改革は大問題だったと考える。
これで自治省と郵政省などが意味なく無理矢理合併統合されたし、経済企画庁の業務は内閣府に吸収され、中期的経済計画や経済白書がなくなり、国民経済についてマクロ・ミクロの両面から政策提言を行う専門省庁が消えて、財務省は万歳を叫んだというのだ。
このことは何を意味しているのか。財務省から見ると、閣議の場で国民経済の観点から財務省の施策に異論を唱えることができる大臣を持つ組織が解体されたのだ。その結果として財務の専横はここから始まったのではないか。
この時に、大蔵省から財務省と名称を変更したが、大蔵省設置法にはなかった省の責務として「財政の健全化」を盛り込んでしまったことは大問題であった。これを容認してしまった政治の責任は極めて大きい。ここから日本の転落が本格的に始まったと言えるほどである。
というのも、省庁設置法にその省の「function」を書き込んだ省はほかに見当たらないのだ。財務省が「財政の健全化」のために省を機能させていくのなら、国土交通省は「国土の均衡ある発展」を目指さなくていいのか、経済産業省は「各種産業の発展と国際競争力の向上」を設置法に書かないでいいのか、ということになるのではないかという疑問なのである。
各省庁は、このセリフを武器に財務省と戦えるのだが、現状は武器を持っているのは財務省だけなのだ。「そんな予算要求をして、財政の健全化が保てるのか」というセリフを財務省に与えてしまったのである。要求側に「それを削減して国土の均衡的な発展ができるのか」との切り返しができる武器がないのだ。
ともあれ、この橋本行革は後世に大きな禍根を残したと考える。さらに橋本政権は後に本人が大反省を述べるほどの、とんでもない緊縮政策を実行したのだった。橋本龍太郎は小泉純一郎との総裁選挙に敗れた後に、次のような反省を述べたのだった。
「私は財政再建をやり国民に迷惑をかけた。私の友人も自殺した。本当に国民に申し訳なかった。これを深くお詫びしたい」。財政構造改革法を制定して、後年度の国債発行額に枠をはめるという「トンデモ法」まで制定したのを大反省していたのだ。
この反省を産経新聞の田村秀男編集委員は「橋本氏は財務官僚の言いなりになっていたことを、亡くなる間際まで悔いていたと聞く」と述べている。あれだけ鼻っ柱が強く、傲慢とも見えた橋本氏がここまで反省したのだ。しかし、その後の内閣・総理がこの反省を引き継ぐことはなく、むしろ小泉純一郎政権はさらに厳しく緊縮・インフラ整備抑制路線に走り、経済の成長を完全ともいえるほどに止めたのだった。
(月刊『時評』2025年7月号掲載)