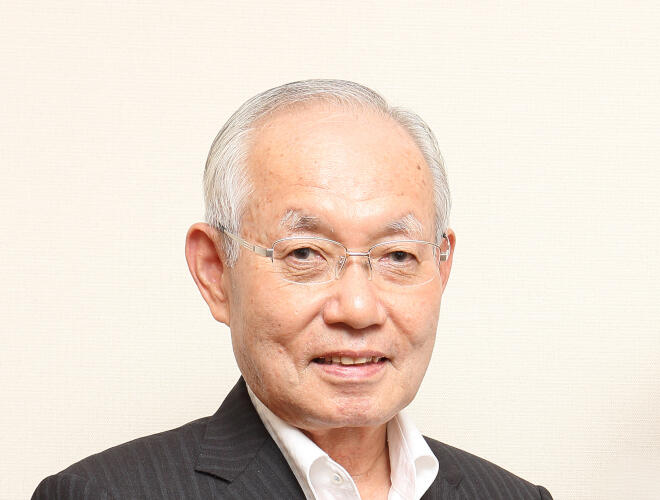
2026/01/06

米国にトランプ政権が再登場したことで、世界は大きく揺れ動いている。
いわゆるトランプ関税をめぐる狂騒は、その典型的な例であり、他ならぬわが国も日米協議に振り回されてきた。
論者によっては、トランプ政権が自由貿易を窒息させ、地球環境問題を軽視ないしは無視し、自国優先主義に走っているとして、諸悪の根源はトランプ政権だと批判している。
しかし、トランプ政権が掲げる自国優先主義の根底に何があるのかを看過して、トランプ政権を批判するばかりでよいのであろうか。
トランプ政権が打ち出すそれぞれの政策の根底にあるのは、これまで共有されてきた「国際社会の在り方はこういうものだ」というある種の常識が転換されようとしているという現実だ。
すなわち、ここで私たちが理解すべき重大事は、米国は新たな「グランド・ナラティブ(大きな物語)」を提示しているということだ。
時代を規定する「グランド・ナラティブ」は、第二次世界大戦後に限ってみても、「米ソ冷戦」「ポスト冷戦」と転換されてきた。
米ソ冷戦時代、私たちは東西両陣営の対立構造の中で、勢力均衡によって平和を保つ一方、東西間の経済関係は閉じていた。
こうした東西対立の構図こそが、当時の「グランド・ナラティブ」であった。
冷戦がソ連崩壊によって終結すると、私たちは自由経済と民主主義がグローバルに浸透していくことで「平和の果実」を享受するのだという「ポスト冷戦」という新たな「グランド・ナラティブ」が登場した。
その下で、実際、中国やロシアのWTO加盟など具体的な動きもあった。
自由経済と民主主義の最終的な勝利によって「歴史の終焉」を迎えたという議論すらあった。
しかし、今、米国の振る舞いが示しているのは、そうした自由経済と民主主義のグローバルな拡大をうたう「ポスト冷戦」という「グランド・ナラティブ」がもはや有効ではなく、「ポスト・ポスト冷戦」とも呼ぶべき新たな「グランド・ナラティブ」が必要だという彼らの認識だ。
自由経済には、フェアなルールが必要であり、皆がそれを守ってこそ健全なマーケット機能が発揮され、良い結果となる。ところが、中国をはじめとする国々は、程度の差こそあれ、アンフェアな振る舞いによって米国が擁護・推進してきた自由経済を「悪用」し、米国の利益を害している。
また、自由経済に立脚した経済成長が民主主義の発展を促すと期待したが、中国は自国の経済発展を共産党一党独裁の継続の基礎とし、あまつさえ、経済力を軍事力の拡大に結び付けて覇権主義的振る舞いによって国際秩序に挑戦し、その不安定化をもたらしている。
自由経済と民主主義を価値としては認めるが、実際には、アンフェアで権威主義的な振る舞いによってシステム自体が傷つけられている。
こうした状況を改善するためには、米国も大旦那のように鷹揚なままではいられない。自国の利益を守らなくては、中国的な権威主義が世界を覆いつくす不幸な未来を招来してしまう。
米国が提示しているのは、こうした論理に基づく「ポスト・ポスト冷戦」という新たな「グランド・ナラティブ」なのではないか。それは、トランプ政権の一時的な妄言ではないだろう。
だからこそ、トランプ政権に近い論者が「日本も、米国か中国かという踏み絵を迫られることになろう」と指摘するのだ。
米国が提示する新たな「グランド・ナラティブ」に対して、その是非を論じることは可能だろう。
しかし、国益という観点からは「良い悪い」の議論よりも、リアリズムに基づいた対応が求められる。
トランプ関税をめぐる日米交渉の行方は本稿執筆時点で明らかではないが、「ポスト・ポスト冷戦」という新たな「グランド・ナラティブ」を提示している米国に対して日本はいかに向き合うのかという大きな課題は、いずれにせよ残っている。
中国、ロシア、北朝鮮と隣接する国土を有し、日米安保条約を安全保障の基軸としている日本。また、日米の経済関係の広さと深さは言うまでもない。
そうした立場にある日本に対して、米国は「現下の国際社会をどのようにみているのか」「日本としていかなるグランド・ナラティブに依拠するのか」と問い掛けている。
そうした大きな問い掛けを見誤り、小手先の対応を重ねることは国益を損なうであろう。
さらに言えば、私たちは、日本自身の問題として、いかなる「グランド・ナラティブ」に依拠して国際社会で振る舞うのかを真摯に考え抜くことができているかを自らに問い掛けねばならない。
日本が主権国家として屹立し、グローバル・プレイヤーとして「国際社会において、名誉ある地位」(日本国憲法)を獲得するための前提条件の一つは、まさにここにある。
(月刊『時評』2025年7月号掲載)