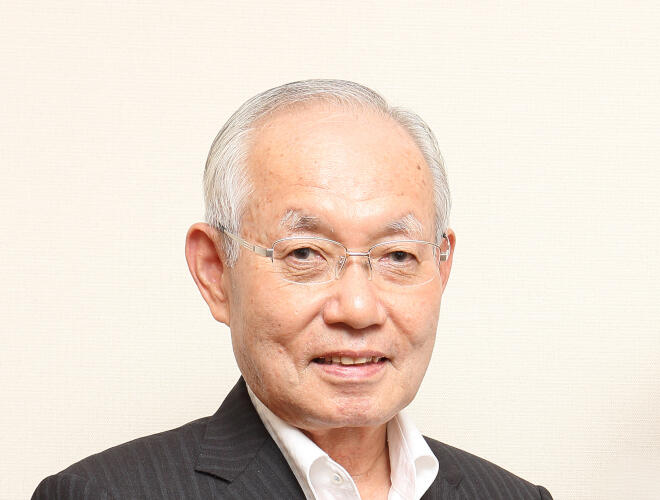
2026/01/06

世界には四つの国しかない。「先進国」と「途上国」と「日本」と「アルゼンチン」だ。
1971年にノーベル経済学賞を受賞したクズネッツは、そのように喝破した。
先の大戦終結後、焼け野原から奇跡の復興を遂げて「先進国」の仲間入りを果たした日本のような国はなかった。
他方で、アルゼンチンは、19世紀後半から20世紀前半にかけて農産物輸出で巨額の外貨を獲得し、第一次世界大戦前には世界有数の富裕国となっていたが、急速に経済を悪化させて、今やGDP規模では世界第24位となっている。
猛烈なインフレと国家財政の悪化が繰り返され、アルゼンチンがこれまでに経験したデフォルトは実に9回に及ぶ(直近は2020年。その後、10回目の危機はかろうじて回避された)。
社会と経済の混迷が続く中で、23年11月には、右派政党出身のハビエル・ミレイ氏が大統領に当選し、深刻な経済危機を脱するため、自由市場の原則に基づく大胆なショック療法を導入している。
なぜ、アルゼンチンは、世界有数の富裕国から急速に転落したのか。
多くの論者が指摘するのは、第二次世界大戦後に長く続いたポピュリズム的政策の影響だ。
アルゼンチンでは、第二次世界大戦後に主に下層労働者が熱狂的に支持するペロン大統領の結成した「正義党」(ペロン党)が一大勢力となり、労働者向けの人気取りの色彩が濃いポピュリズム的な政策を採用した。
ペロン主義と称される左派的政治理念の下、具体的には、医療や教育の無償化を進め、年金受給額を引き上げ、国民への現金給付を重ね、さらに労使関係に介入して労働者の賃金を上昇させようとした。
当然ながら、国家財政は悪化したが、他方で、本来、独立した中央銀行の責務である金融・為替政策もまた、適切に実施されず、猛烈なインフレと通貨安に苦しむ結果となった。
実に国民の40パーセントが貧困層であるとも言われる状況の中で、かろうじて決選投票で選出されたのが、現在のミレイ大統領である。
今後、ミレイ政権が、財政政策と金融政策の正常化に成功すれば、国際金融市場での資金調達も円滑になり、貿易や投資も拡大するであろう。
しかし、自由経済主義に基づく経済改革の「痛み」に国民が耐えられなくなった場合には、再びポピュリズム的政策を掲げる政権が復活し、経済が悪化していく恐れもあると指摘されている。
実に、アルゼンチンの歴史がその恐れを杞憂とさせないのである。アルゼンチンでは、今も「正義党」は有力な政治勢力であり続けており、歴史を振り返れば、これまでの政権も右に左にと揺れ動いている。
翻って、わが国は、ランクダウンしたとはいえ世界第4位の経済大国であり、G7のメンバー国であり、安定した世界有数の富裕国だ、と思っている人々が多いであろう。
あるいは、クズネッツがかつて喝破したように、アルゼンチンとは対極にある成功した国だと自負するところもあるだろう。
しかし、それらは過去の実績であって、将来を保証するものではないこともまた当然である。わが国が急速に転落するリスクは直視せねばならない。
多くの論者が指摘するアルゼンチン経済の悪化要因をあえて再度述べると、医療・教育の無償化推進、年金受給額引き上げ、国民への現金給付、労使関係への介入による給与引き上げ、等々の「受ける」ポピュリズム的政策であり、また他方での金融・為替政策の失敗だ。
ここで、あえてこれらの要因を再度述べた趣旨は明らかであろう。わが国への警鐘である。
かつてカール・マルクスは「歴史は繰り返す。一度目は悲劇として。二度目は喜劇として」と述べたと言われる。
わが国では、税収の「上振れ」が発生したことをもって「税金の取り過ぎ論」まで聞かれるが、税収の上振れはインフレの予兆ないしは初期事象である。
実際、足元での消費者物価指数は上昇を続けており、生活実感としても、もはや日本経済がインフレ期に入ったことは否定しがたい。
インフレ抑制のために日本銀行が本来の責務を果たすならば、金利は上昇し、将来に向けて国債利払いは増加する。
実際、金融市場では、超長期国債の利率が急上昇(価格が下落)して、警告を発するに至っている。
こうした中、日本銀行は、国債購入減額のスピードを緩めるという決定を行わざるを得ない状況に立ち至っている。
アルゼンチン経済の立ち直りを願うが、それ以上に私たちは自らの状況を冷静に、しかし、現実的な危機感をもって、アルゼンチンの歴史をも踏まえて、点検すべきではないか。
政府と日本銀行には、国民への説明を尽くして、歴史的検証に耐える政策決定と実行を期待したい。後世において「笑うしかない」喜劇を決して演じてはならない。
(月刊『時評』2025年8月号掲載)