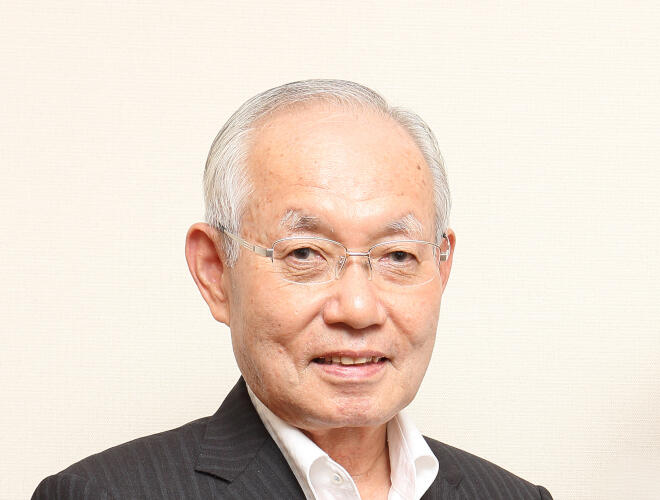
2026/01/06

私たちは、認知バイアスから逃れられないらしい。
都合の良い情報ばかりを無意識に集めたり(確証バイアス)、一部の特徴に引っ張られて全体的な評価を歪めてしまったり(ハロー効果)、情報の提示方法によって判断や意思決定が大きく変化してしまう(フレーミング効果)等、物事を客観的に判断し、合理的な思考を行うことができなくなる認知バイアスの実例は多い。
そうした認知バイアスの一つに、自分にとって都合の悪い情報を無視してリスクや異常性を看過してしまう正常性バイアスがあるが、日本は指導者のみならず、集団としてこの正常性バイアスにとらわれているのではないか。
異常なことが頻発し、合理性や規範からの逸脱が多発しているというのに、多くの人々は、今日は昨日と同じで、明日は今日と同じだと信じているかのようだ。
しかし、虚心坦懐に私たちの現実を見れば、さまざまな面で、恐ろしいほど異常で不都合な状況が数多く見られる。
例えば、異常気象だ。
今年の夏、40度を超える酷暑を経験する一方で、35度超えの「猛暑」は普通のことであるかのように扱われた。
熱中症に気をつけましょう、という紋切り型の言葉が飛び交ったが、そもそもこの異常気象をどうしたらいいのかについては、仕方ないですねと素通りされている。
それどころか、化石燃料の消費が地球温暖化と気候変動の原因だと言いつつ、ガソリン価格の引き下げに躍起となり、また、米国産LNGの大量購入を約束した。
気象については、集中豪雨も「今まで経験したことがない」という説明付きのものが頻発したが、こちらも「命を守る行動をとってください」という決まり文句はたくさん聞いたが、そうした気象に対応するためのインフラ整備などの対策については議論があまり聞かれなかった。
あるいは、猛烈な勢いで減り続けるわが国の人口動態だ。
日本人の人口は、ここ1年間で90万人以上の減少となり(ちょうど和歌山県の総人口分が減少したようなインパクトだ)、平成21年の1億2707万人余りをピークに16年連続の減少となっている。
こうした人口減少は、明らかに危機感を持つべき異常事態だが、長らく少子高齢化と聞き続けて慣れたためか、人々の危機感は薄いようだ。
地方公共団体は子どもを奪い合うような政策を競っているが、それでは国全体としての人口問題は解決しない。他方で、国のこども家庭庁は創設されたことが最大の成果と揶揄する声さえある。
さらなる異常性の例は、膨大な借金を抱える国家財政だ。
普通国債残高は増加するばかりで、2025年度末には1129兆円になると見込まれている。
GDPに対する比率は実に250パーセント程度となっており、G7諸国において飛び抜けた水準となっている(2番目に比率が高いイタリアは約140パーセント、最も低いドイツは約60パーセント)。
しかも、日本国債のおよそ半分は中央銀行である日本銀行が保有するという異常な状況にある。
こうした財政状況のため、近年の予算においては、社会保障関係費と国債費と地方交付税交付金等で歳出全体の4分の3を占めるようになっており、まさに「貧すれば鈍す」の典型となっている。
現下のマクロ経済環境で財政を拡張すれば、インフレは管理不能なレベルに達する恐れすらあるが、それでも、給付だ、減税だ、という声はなくならず、政治はポピュリズム的傾向を強めている。
そうした政治状況もまた、異常といっていいはずだ。さまざまな政局的な動きはあっても、国家百年の計を国民に正面から問う真摯な政治は見られない。
そうした一方、日本経済も異常といっていい経路をたどっている。
プラザ合意後、円高不況を恐れてバブル経済を生み、その弊害に耐えかねて一気にバブルをつぶした後は長期低迷に甘んじてきた。
かつての経済大国は「露と落ち露と消えにし」で「夢のまた夢」となり、私たちの豊かさを規定する一人当たりGDPは、名目で世界第38位(IMF)、購買力平価換算で世界第45位(世銀)まで落ち込んでいる。私たちは貧しくなった。
かつて世界第2位であった(第1位はルクセンブルクで、実質的には第1位といっていい)ことを思えば、わずかな期間でこれほどの凋落は異常であろう。
これほどまでに迅速な零落を諸外国は冷淡に見つつ、大安売りとなった日本を買い漁っている。
こうした日本の状況を異常と言わずして何を異常というのか。
規範も合理性も逸脱していく異常性に私たちは慣れてしまい、持つべき危機感を持たずにいるのではないか。
日本という自分が乗っている船全体が沈み行くことを認知しないで、自己利益のみに拘泥し、目先の弥縫策を求める姿は、悲劇であり喜劇である。
認知バイアスを越えて現実を直視し「危機感がないという危機」を克服すべきだ。
(月刊『時評』2025年10月号掲載)