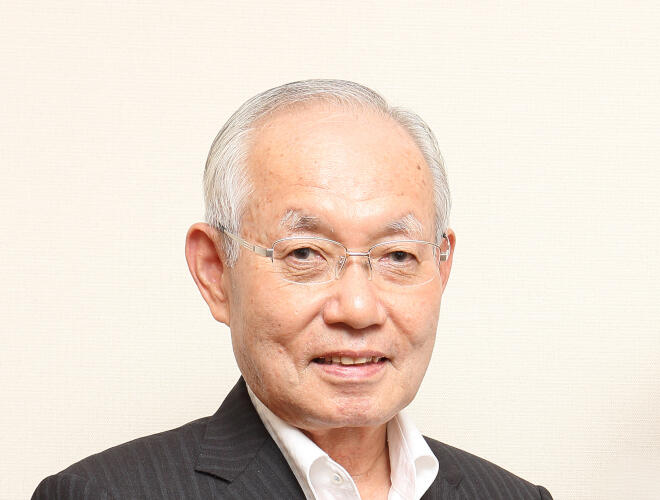
2026/01/06

2022年9月23日、リズ・トラス英国首相(当時)は、大規模な減税政策を柱とする一連の財政政策であるミニ予算「成長計画2022」を公表した。
所得税率の引き下げや法人税増税計画の中止など、停滞が続く英国経済の立て直しを目的とした財政負担の拡大を図るものであった。
当時の英国を振り返ると、景気は低迷、実質賃金はマイナスとなっていた。
他方で、政治の混乱から短期間での政権交代が続いており、財政拡張を求める声が政治的に拡大しやすい状況であった。
しかし、この「成長計画2022」は、財源論なき財政拡張であったため、財政悪化の懸念から英国債利回りが急上昇(国債価格は下落)、発表直後から金融市場は大きな混乱に陥り、通貨ポンド、国債、株価の「トリプル安」に見舞われた。
いわゆる「トラス・ショック」である。
こうした状況にあって、独立性の高い英国中央銀行は、英国の長期国債を同年10月14日まで(本当に短期である)無制限に購入する緊急対応を発表した。
また、根本的な原因である政府の財政拡張計画に関しても、クワーテング財務大臣(当時)が解任され、後任となったハント新財務大臣は、就任早々となる10月17日に「成長計画2022」の大部分の撤回を発表した。
トラス政権の財政拡張計画によってもたらされた英国内からの資本逃避という危機は、政治的判断としての財政拡張に対する市場からの「反応」(もっと厳しく実態に即して言うならば「反撃」)としてもたらされたものであったが、トラス首相が英国史上最短となるわずか49日間で退陣するという形で収束した。
共産主義ならぬ資本主義を掲げる自由経済システムの下にあって、政治が経済に対してできることには限界があるのだという単純な真理を再確認させる事件であったといえるだろう。
翻って、わが国においては、7月20日に実施された参議院選挙において、各政党とも濃淡はあれ、給付や減税といった財政拡張的な主張を訴えてきたところであり、これからその「手形」をどうやって落とすのかという難題に政治は直面することになる。
すでにわが国の財政事情は、国際的に見ても突出して悪化しており、中央銀行である日本銀行も赤字国債をこれ以上抱えきれないほど抱えている。
1000兆円を超える国債残高のおよそ半分を日本銀行が保有するという異常性に私たちは慣れてしまっているようだが、その出口は明確となってはいない。
一部には、日本国債は国内で消化できておりまだまだ大丈夫、現にこんなに国債を発行しても何も起きていないなどという無責任な財政拡張論も聞かれる。
これでは、まるで、今日まで生きてきたから明日も生きている、という永遠の寿命を主張するようなものだ。
論より証拠ではないが、現に、参議院選挙前から、日本国債は売られ続け、長期金利は急上昇している。借り換え債の発行・消化も従来通りとはいかないと伝えられている。
また、為替相場も円安傾向が続いて物価高を後押ししており、私たちが貧しくなる要因となっている。
株式市場だけが買い越し傾向が続いているが、これもNISAブームに加えて、円安の波に乗った海外からの資金流入の寄与が大きく、日本企業を部分的に外資に安値で切り売りしているに等しいとも言える。
こうした状況は、市場からの政治に対する警告に他ならないはずだ。
しかし、その危機感を私たちは十分に持ち合わせているだろうか。
日本版「トラス・ショック」が杞憂となることを願うが、その恐れは高まる一方のように見えることも否定しがたい。
むしろ、ショックという急激な形ではないが、ある意味で日本的な緩慢な形で市場からの反撃は始まっていると見るべき状況なのかもしれない。
今回の参議院選挙の結果は、若年層を中心に変化を求める声が強かったということであろうが、「フライパンから飛び出したら火の中」(Out of the frying pan into the fire)ということになってはならない。
変化には、もちろん良い方向への変化もあるが、悪い方向への変化もあるのだ。
そもそも参議院は「良識の府」であるべき存在である。
いずれの政党、政治家も、自己利益のために国を誤ることがないように国家・国民のために真摯に考えて判断を下し、歴史の法定で断罪されることがないように願いたい。
もちろん、国家・国民を意図的に混乱に陥れてやろうという政党・政治家はいないだろう。
しかし、「地獄への道は善意で舗装されている」という。トラス氏にしても、決して混乱を招きたかったわけではないはずだ。
現下の状況にあって、政治には、国家・国民のために、賢明なる判断を切に求めたい。
(月刊『時評』2025年9月号掲載)