
2025/12/05
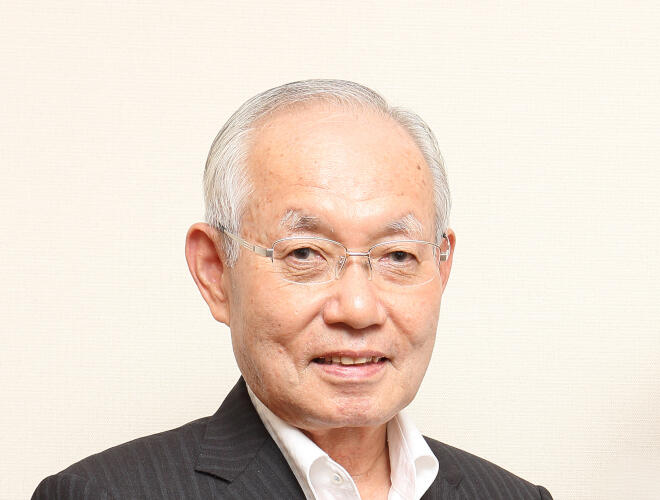
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
ここではG7などの世界の先進国とまったく異なる日本人のインフラ認識のレベルの低さと、そこから来るインフラ整備費の極端ともいえる減少の状況を何度も紹介してきた。高度経済成長期に整備されてきたインフラがまもなく供用後50年にもなって、過去の経験に照らしても丁寧な点検・検査が必要になってきているにもかかわらず、管理費用を削減するのみならず、点検検査手法の開発、あるべき検査頻度の研究も怠ってきた結果が、八潮市の陥没事故に象徴されているとも述べてきた。
「過去の人々の整備努力の恩恵を受けているのにもかかわらず、次世代に良好なインフラを引き継ごうとしていないという『現世代の怠慢』を象徴している」のではないかと考える。その怠慢の基礎にあるのが「財政が厳しいが、国債発行は次世代へのツケとなる」というデタラメな財政の理解なのだ。
オールドメディアは「国債は国の借金」とそろって叫んでいるが、岸田総理(当時)は本会議で「国債は国の借金か」と問われ、明確に「国の借金ではありません」と答弁しているのだ。
現世代の次世代に対する無責任を驚愕的に感じさせられたのが、北海道のJRネットワークの激減というべき縮小だった。50年前には4000㎞あった北海道の鉄道は、2016年には2500㎞へと減少し、直近ではさらに200㎞が廃線となって2300㎞になったというのだ。
人口減少が続く現状に、JR北海道はこの2300㎞も維持できないとして、将来的には1300㎞の維持がせいぜいだというのである。近い将来、北海道には札幌と函館周辺にしか鉄道がないという惨状を呈することとなるのである。
このことは何を表しているのか。第一に、これは大正・昭和の先人たちの鉄道整備にかけた情熱と努力を廃棄していっているのだ。第二に、われわれの世代まではその先人の努力の恩恵を受けてきたが、将来世代にはその恩恵を与えないと決めたということなのだ。
この第一と第二は端的な世代責任放棄である。
第三に、最近ロシアは北海道は自国のものだとトンデモ級の暴言を吐いているが、特にオホーツク海側からレールをはがしているということは、「いざというときの師団単位での北海道北部への鉄道による兵員輸送を不可能にした」ということだ。
この論理は「安全保障概念」がほとんど皆無の日本では、「何なのそれ」という感じなのだが、ドイツやイギリスの鉄道インフラ管理概念では、安全保障は一丁目一番地の重要事項なのだ。鉄道の民営化は日本がこれらの国に先行したが、彼らが日本のマネをしなかったことがある。それが、いろいろ紆余曲折はあったが、「レールや信号機システム」は公共保有としたことなのだ。両国の旅客会社や貨物会社は「使用権を借りている」のだ。現にイギリスでも旅客会社が経営破綻したことがあるが、公共の保有機構は条件を変えて別の旅客会社にインフラシステムを利用させて乗り切っている。
これはレールなどのインフラは安全保障のツールであり、それは公共保有・公共責任が基本だという信念があるからなのだ。フランスの高速道路も民間会社が運営している例が多いが、ここも道路本体は国のものである。民間会社は借りて運営しているのである。
筆者が道路公団民営化議論の渦中にいたとき、民間の経営者が有識者として、いろいろと注文を付けてきたことがある。その中に「資産を持たない民間会社はあり得ない。道路インフラは民営化された会社が保有すべきだ」という強い主張があった。
国家存亡の危機に際して、「道路インフラを毀損する恐れがあるから防衛車両は走行させない」と言わせない仕組みが欠かせないというのが西欧諸国の常識なのだが、日本は異なるということであった。安全保障の概念欠如はこのように社会の各部に浸透している
八潮市の大陥没事故に戻るが、この事故は良好な状態で管理して次世代に受け渡す努力を怠りながら、「財政が厳しいからね」とうそぶき、維持管理費や管理担当者の人員削減に励んできた現世代優先の将来世代無視の結果だったのだ。
この事故は道路下の空洞探査がまともに出来ていなかったことが最大の問題で、深部にできた空洞が少しずつ大きくなって地表面近くまで大空洞化していたのに発見できなかったという言い訳のきかない事件で「荒廃する日本」の始まりだったと考える。
空洞探査装置の高度化や探査の頻度など大反省すべきことが多い。道路、下水道、上水道をすべて所管する国土交通省の責任はきわめて大きい。
話は全く変わるが、大騒動となった103万円の壁の話も、178万円にすると7兆円もの歳出負担となるというが、話がまるで逆で、最低賃金に連動するなら毎年7兆円も取るべきではない税を貧困層から収奪してきたということだ。これこそが若い層の結婚意欲や子育て願望を破壊してきた問題の本質なのだ。日本政治は議論すべき主題を間違えている。
おまけに近年の一般会計税収を見ると、2025年の見込みは77・8兆円で前年の2024年から4・4兆円も伸びて、これは2009年の38・7兆円(ここ30年で最低の税収だった)から見ると、年々順調に39・1兆円も増えて倍増したというレベルなのだ。この国の政治は何を議論しているのだろう。つまり、ここでも次世代への責任放棄があるのだ。
「国民が福利を享受できるようにすること」が政治家の役目だと憲法は前文に規定していることを考えると、1995年には660万円だった日本国民の世帯所得が、2021年には545万円にも下がってしまった責任をどう考えているのだろう。
このようにいろいろ見てくると、「財政が厳しい」と言って将来世代(現世代もだが)への責任放棄の時代を過ごしてきたことがわかるのだ。財政を立て直すのには経済成長するしかないことを理解できなかったのだ。1995年の財政危機宣言から歳出削減主義に走った日本は、スイスのIMDの競争力指数でも、かつては1位だったのだが、直近では世界ランク38位という転落ぶりで、韓国のはるか後ろに位置する有様なのである。
(月刊『時評』2025年6月号掲載)