
2025/12/05
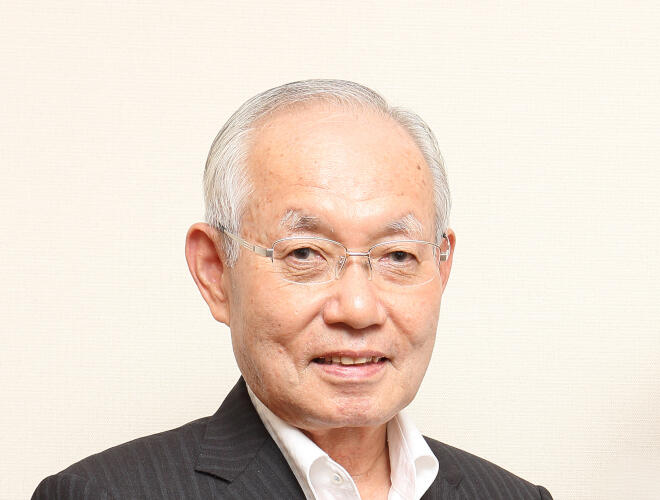
多言なれば数々(しばしば)窮す(老子)
――人は、あまりしゃべり過ぎると、いろいろの行きづまりを生じて、困ったことになる。
30年にもわたって進む国民の貧困化と、日本経済(端的にはGDP)の著しい国際的地位の低下にはいくつも背景があり、小選挙区制の導入による国会議員の「関心領域の狭さ」と「知的レベルの劣化」「専門分野の欠如」が日本の破壊に大きく貢献してきたと考える。
さらに2001年の省庁再編において大蔵省が財務省に変わった際に、全省庁の中で唯一、省のFUNCTION(国語辞典的には、機能・働き・効用・役目・役割)を規定したのがこの省だけで、「財政の健全化」を省の設置理由としたことは問題だった。
この規定は大蔵省時代にはなかったもので、FUNCTIONを財務省の設置法に書くのであれば、以前にも示したように他省庁にも必要なはずなのにそうならなかったために、まるで「行政組織全体の設置目的が財政の健全化となった」かのようなのだ。
加えて大きいのが、2001年の省庁再編に際して一府十二省という枠にこだわったために、大臣庁であった国土庁や経済企画庁が実質的に消えていったことだった。実際にインフラの整備を行うところと分離して、専門的に国土整備の目的や理念を考える小さいながらも大臣庁であった国土庁を消して、国土交通省という実施官庁の中に入れてしまったのだ。
これも問題だったのだが、さらに大きな問題だったと考えるのが、同じく大臣庁であった経済企画庁をなくしてしまったことだった。経済企画庁長官は、通常国会において「経済演説」を行い、安全保障会議に参加し、その官僚は日本銀行の政策委員会に出席するなど重要で大きな権限を有していた。大臣庁であるから閣議で大蔵省に異論を唱えることもできたのだ。
また、「経済白書の編集」を行うなど、「権限がない分、中立的な姿勢で国民経済のミクロ・マクロの両面から分析し、それは経済政策へ大きな影響を与えていた」と評価されていたのだった。
省庁再編の少し前に、作家で評論家の堺屋太一氏が経済企画庁長官だったことがある。彼などは大蔵省への遠慮などもなく、有力政治家の顔色などを窺う必要もなかったから、経済政策についての自分の主張を貫いていったのだが、こうした存在は実に貴重なものだったのだ。
さて、大蔵省時代にはなかった省のFUNCTIONとして財政の健全化を持たせたのなら、新しい一府十二省時代には全省庁にこうした規定を入れるべきだったと考える。その「各省の存在理由」規定がないために、先に示したように「財政の健全化」に対抗できる予算要求の論理が官庁に存在しないのだ。
これが「財政の健全化」の一人勝ちを生み、経済成長も国民の豊かさへの追求も財政均衡論の前にすべてなぎ倒されて「国家が存在する理由」を不明なものにしてきたのが、1995年の財政危機宣言から2001年の省庁再編に至る流れだったと考えるのだ。
考えてみると、この国には「FUNCTIONへの理解がなく、これを規定しているものが極めて少ない」ことがわかるのだ。筆者の世界で一つ上げると「インフラの評価方法」である。
わが国では、新たなインフラ(道路の延伸など)を企画すると、「費用対効果分析」を実施しなければならないことになっている。いわゆる「B/C=Benefit/Cost」評価である。これが、わが国ではインフラの新規投資の金科玉条的基準になっているが、「しかし」と言わなければならないことがある。
2011年に三陸地方を襲った東日本大震災を経験して、東北の三陸側にも東北の中央部を縦貫している東北縦貫道路のような自動車専用道路の整備を促進しようというムードが超党派的に盛り上がった。三陸道は30年も前から建設してきたのだが未整備区間が多く、残りを全線一斉に着工するわけにもいかず、手順としては「区間ごと」に新規採択していくことになる。
例えば、三陸縦貫道貫通のためには「青森県の八戸市と岩手県の久慈市」を結ばなければならないが、どちらの市も大きな人口を抱えているわけでもなく、従来から県境を越える交流が盛んだったこともなかったから、なかなか大きなBenefitが見込めなかったのだ。
そのため、大地震の前までは整備が進まなかったのだが、震災後、超党派で一気に推進することとなり、最近になって「三陸側の縦貫道路としての自動車専用道路」が完成したのだ。
ということは、「北東北から関東まで、東北縦貫道路に加えて、三陸側にも(日本海側にも)高速の自動車道路」が必要ではないかという議論が「交通量をさばいて便益を稼ぐ」という論理だけでは、まるで不十分であったということなのだ。
こうして三陸縦貫道路がつながってみると、「東北縦貫道路とは異なり、三陸の海に近いこと」などを理由とした企業の立地などが進み始め、地域が活性化してきた。つまり、インフラの整備・供用効果なのだが、こうしたことはまるでインフラの採択の際の基準とはなっていなかった。これはインフラを過小評価してきたことになっていると認識しておく必要がある。
ところが、ヨーロッパでECがEUになる過程で議論されたというインフラ整備の論理を知って腰を抜かすほどに驚いたのだ。かなり昔のことになるが、EUは広域的な国家連合を形成するに当たり、今後のインフラ政策をどのような論理で進めていくかを、広範な分野の専門家を集めて喧々諤々の議論をしたのだった。
その結果、取りまとめられたのが「そのインフラ整備が、①ヨーロッパ全体の経済成長に寄与するのか、②ヨーロッパ全体の環境改善に役立つのか、③ヨーロッパ全体の人々の機会の公平性の拡大に貢献するのかの三つの観点から判断していこう」というものだった。
これは、わが国の「費用対効果分析」などをはるかに凌ぐFUNCTION による判断なのだ。すべてに当該箇所での効用ではなく、「EU全体の」とかかっていることも重要だ。
経済的効用が費用を上回るから建設するかどうかを判断しようという日本の考え方などをはるかに超える「インフラの地域国民全体への貢献度評価」となっているのだ。
わが国は、経済的にも、競争力的にも、国民の豊かさ的にも、とにかくありとあらゆる分野で他のG7国などに大きく水をあけられてきており、すでに世界からの評価は発展途上国(転落途上国)並となっているが、知的レベルでも大きく落伍していると考えざるを得ないのだ。
(月刊『時評』2025年8月号掲載)