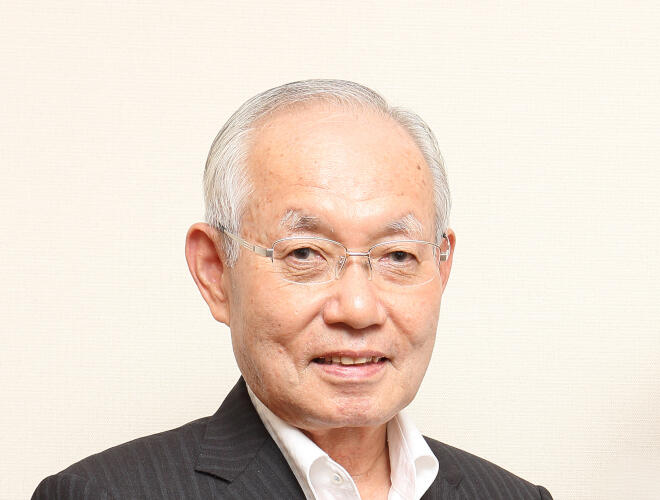
2026/01/06

なんと新政局は、自民・立民両党の党首が最長老同士という顔合わせになった。安倍・黒田のアベノミクスとそれを盲襲した岸田の超低金利政策は、一億総中産国・日本を破壊する〝失われた30年〟の総仕上げになった。社会の貧富二極化とかつての高度成長の遺産の優れたインフラのいっせい老朽化に、日本政治はどう立ち向かっていけばいいのか。
新鮮味のない〝新横綱〟同士
石破茂自民党総裁・野田佳彦立憲民主党代表を軸とする新政局の枠組みが成立した。
政権の座を争う、という建前の与野党の第一党の党首がほぼ同時に交替するのは、そう珍しくないのかもしれない。しかし片方は、一度は総理を経験したとはいえ総選挙に惨敗して引責辞任し、表舞台から退いていた人物の出戻り。片方は過去に総裁選に出馬すること4回。いずれも敗退して5回目の今回が〝最後の挑戦〟と自ら謳った結果、同情票も集めての辛勝。これでは一応〝新横綱〟の顔合わせとはいえ、新鮮味はない。
両者の国会質疑も、議事録を繰って見れば野党の論客とどこかの大臣、不慣れな首相と野党質問初体験の前政権党議員、といった組み合わせで何回か出てきていてもなんの不思議もない。本来ならまず一党の行事である党首選が行われ、次いで公的行為である特別国会による首班指名、新内閣の組閣、認証式と続いて新政権の態勢が整うとともに国会が再開され、まず新総理の所信表明演説とそれに対する各党代表質問、そして一応は衆参両院の予算委員会で新総理・新大臣と野党論客の質疑と答弁の応酬があったうえで、新政権の信を問う総選挙になるのが自然だろう。
しかし今回石破は、両院の予算委員会は抜きにして、国会の施政方針演説と各党代表質問と、形ばかりの党首討論で済ませた。石破が自民党内の手続きで総裁に決まったのが9月27日。それに伴う自民党新執行部の大まかな人事の決定が翌28日。特別国会の招集と石破新総理の指名、新閣僚の銓衡と任命及び認証式が10月1日。10月4日に新首相の所信表明演説、5・6の土曜・日曜は休んで7日と8日に衆参両院の各党代表質問。9日に両院で交替開催の慣例で今回の当番・参院での党首討論を終え、衆議院本会議を開いて議場での解散詔書の伝達と朗読。ここで自民党議員による冴えないバンザイがあって解散の運びになった。
期待感の薄さですんなり進行
10日と11日には前内閣時代に日程が決まっていたラオスで開かれたアセアン(東南アジア諸国連合)の首脳会議に、石破が首相として初めて外交舞台に登場するという番外行事を経て、15日の総選挙公示、27日には投開票だ。異様といえば異様、不自然といえば不自然な話で、石破自民党新総裁が実現してちょうど1か月の総選挙になった。この間まだ党総裁になっただけで国会の首班指名は受けておらず、すでに死に体とはいえ形式上は現役首相の岸田の手に解散詔書の発出・総選挙告示詔書の発出という、憲法に基づく天皇の国事行為の発動を奏請する権限が残っている状態だったにもかかわらず、石破が軽率・軽躁にも解散ー総選挙の日程に言及し、立憲民主を始めとする野党や与党内からも総抗議を食らうという醜態を演じた。
この〝暴走〟に対して一部の偏向新聞・左傾放送局が反対機運を煽って見せたものの、世論がロクに反応せず事態がすんなり進行していったのは、両党とも長く棚晒しだった古手が党首に選ばれ、見慣れた顔合わせになった期待感の薄さの反映だろう。この〝番付〟の〝取り組み〟は初めてとしても、2人の顔合わせはさんざん見てきた政界の〝桟敷衆〟が沸く要素は初めっからない。それなら決まりきった形式的な段取りに時間をとるよりも〝儀式〟なんかさっさと終えマトモに政権を機能させろ、という空気だったからだろう。
世界の激動、日本の太平楽
世界の動きはここ一両年、激しさを加える一方だ。プーチン・ロシアによるウクライナ侵略。イスラム過激派・ハマスがイスラエル南西部の農耕住民に対して突如奇襲侵略攻撃に出て、住民1200人余を殺戮、250人以上を拉致したテロに端を発した、イスラエルとイスラム・ゲリラの戦闘に、ゲリラを陰で支援するイランなど中東の諸政権の思惑が絡む、複雑微妙な展開。ひところは南太平洋への進出が目立っていた習近平・中国が、一転してフィリピン近海から台湾周辺に及ぶ東太平洋で蠢動しはじめたこと。これらが引き起こす全ヨーロッパ、全中東、もちろん全東アジアに及ぶ緊張と、それらを制御・抑制する立場のアメリカの、大統領選のさなかという事情があるとしても極端な機能不全。加えて原油・石油製品、基礎食糧品をはじめとする国際商品価格の上昇に、それが齎す金利の激動が伴っているのが、最近の世界の姿だ。
ところが日本は、安倍晋三ー黒田東彦コンビがアベノミクスを自画自賛し、人口減・市場縮小に応じて経済成長から成熟社会の構築へ向けて抜本的な路線転換を試みるべく、前途の苦難に正面から対応する施策にきっぱり転換しようとせず、過去の成長遺産を漫然と食い潰すという、安逸一途の気楽な政策運営を続けた。さらに菅政権の1年を挟んで登場した岸田政権は、そうした姿勢を改め金利操作を軸に中間層の安定を最優先する欧米の趨勢に合わせて修正するどころか、安倍の脳天気ぶりに輪をかけて、北朝鮮の核武装化という安全保障上の大きな変化が新しく生じているのに対する方策の基本的な検討すら放棄したまま、太平楽を続けた。
低金利による日本の二極化
欧米はここ10年ほど、言わず語らずのうちに呼吸を合わせてデリケートで機敏な金利調整による経済対策をとっている。一度はマイナス金利や、ブラスにしても0%台という異様な低率に抑えていた標準金利を、景気動向に合わせて0%台、1%台、2・5%と上昇させ、いまは常識的な範囲である4%台で動いている。そうした機動的な金利操作に、同レベルの経済社会である日本は同調して当然なのに、頑なに金融界や大企業・巨大装置産業にとっては極めて有利でも、生活者国民とりわけ高齢者にとっては、暮らしの基盤である金利の安定など完全に無視した、超低金利政策を延々と続けたのだ。
その結果、欧米の景気回復、とりわけアメリカの好景気の出現とは逆に、平成の元号とともに始まっていた〝失われた30年〟が長く尾を引き、敗戦後の荒廃した〝焼け跡・闇市〟の姿から、激しい勤労を基礎として〝高度成長〟を実現させ〝経済大国〟に仕立て上げた、その果実である貯蓄の金利と公的年金で生活している高齢の中間層とその子弟、一度は世界に一億総中産社会と定評がついていた、日本の誇りでもある幅広い中産階級が崩壊した。いまはDX機器を製造し、日々新しい利用(悪用)技術を編み出して市場に提供する新興成り金層と、そのリテラシーを素早くマスターして利用(悪用)する若者から中堅までのカネだけを追い求める現役の一部、そしてそうした新技術・新機能、新風潮が支配する社会から取り残されて窮民化する層、という形に日本は二極化してしまっている。
DXリテラシーを一応は使いこなす若者層にしても、景気の低迷と省力化で必ずしも満足できる就職機会が得られず、安易な手段で高額のカネを掴んで時代の風潮である豪奢な快楽に身を浸そうと考え、自らが編み出した手口でコンピュータ利用詐欺を〝創業〟したり、そこまでのチエはないまでも、特殊なシステムを利用して身元が割れにくい闇アルバイト求人に応じ、悪党の指示に従って強盗殺人を働くケースが、関東一円で激増して広範囲に深刻な社会不安を起こしている。
世襲を筆頭とする今の政治家の正体
一口に経済成長といっても、〝教祖〟の池田勇人は〝物づくり〟〝人づくり〟〝国づくり〟を一体で捉え、勤勉な労働で造られた新機軸の精密堅牢な工業製品を、まず輸出して日本経済の基礎体力を強化し、やがてそうした製品を国内に流通・普及させて国民生活を向上させるのが、敗戦日本の復興を世界に改めて認知させる道だ、と説いた。
しかし岸田は、池田が同志を集めて作った本来は彼一代限りの会の呼称だったはずの、道学者・安岡正篤の命名による〝宏池会〟が自民党保守本流のブランド化しているのに目をつけ、そこは代議士3代目の抜け目なさ、かつて父親が一応は消滅寸前の〝宏池会〟に属していた縁を根拠に、この会の嫡流と自称した。加えて、俄成り金国家・中国の民衆の日本観光兼買い物渡航の大波を頼みに、今後は勤労・工業立国ならぬ〝観光立国〟つまり見世物と買い物のゲイシャ立国を目指そうとする体たらくだった。
この岸田の姿勢には、安倍・黒田に始まるゼロ金利の固定化とともに、許し難いものがあった、と筆者は考えるが、安倍、そして岸田は退陣表明後の〝死に体〟総理に落ちぶれても、これからは貯蓄でなく投資の時代だ、とほざいた。しかし先代や先々代の代議士がどんな情況か知らないが、どうせよからぬ手段で作ったカネを番頭なり出入りの株屋に縁故運用させた成果の安逸を貪って育ったのだろう、ともに三代目代議士の安倍や岸田はいざ知らず、仮にも一定の教養と識見、そして自らの労力や知力で相応の稼得能力を持つ人間は、証券投資や不動産投資などはヤクザのやるバクチであってカタギの人間のすることではない、と心得てきた。
そうした分別・認識がないのが、いわゆる世襲政治家を筆頭とする多くの政治家の正体で、今回の党首選びも与野党を通じて、いまの内外の緊張を無視した無為無策の空想的〝平和〟政策と、いまの崩壊に瀕する国家財政では到底実現できるはずのない経済成長・所得増加・財政資金の大衆に向けたバラ撒きを叫ぶ政党・候補者ばかりが並んでいて、いまこそ国民が心を一つにして新しい国防・外交態勢の確立と、そのために国民が汗を流して敗戦からの国家再建に取り組んだ歴史を想起し、厳しい財政強靭化を図るという考え方は、与野党・保守革新の政治家だれ一人として示していない。これには呆れ返るだけだ。
次回に期待の中堅さえ見当たらず
今回の党首選びには、政界の世代交替につなげる、という考え方もあった。それには理由も根拠も意義も必要性もあったといえる。しかし今回の党首選挙を例にとっても、先行した立民の4人、自民は最終的に9人になった候補者の顔触れは、高齢者ばかりだった。今回はムリとしても、ここで善戦すれば次回は楽しみだ、と思われる中堅の人材さえ、ロクに見当たらなかった。
先行した立民は当初、元・前・現代表が総並びで名乗りを挙げただけだった。これでは毎度ヤクザ映画でお馴染みの、冴えない親分が総出演するサヤ当てと駆け引きのドタバタ劇にしかならない。しかもこの3人のうち最も若い候補は、現代表であるにもかかわらず20人の推薦議員集めに苦労し、届け出締めきり前夜にやっと確保して側近と思わずバンザイを叫んで乾杯した、という体たらくだ。もう一人はかって参院選で共産党との相互推薦による議席増を主導し、世間から〝立憲共産党〟と批判された失脚からの回復過程だ。これでは格好がつかない、という独走状態の野田の発言で、東京都議会の一年生女性がたぶん売名が主目的だろうが、代表選に名乗りを上げたものの、当然のことながら問題にならない。野田が独走して勝ち上がった。
しかしそれは、総裁候補として9人が立っていた自民党にも影響したに違いない。9人は過去に総裁に挑戦して敗退した経験がある〝小石河〟こと、小泉進次郎・石破茂・河野太郎に、高市早苗を加えた古参が4人。林芳正・上川陽子・加藤勝信・茂木敏充、いずれも一定の専門領域では手腕に定評があるが、岸田を支えた林、安倍を支えた加藤、いささか高齢の上川、現に幹事長の茂木と、いずれも今回は手を挙げにくかった中堅が4人。9人の中ではI人だけが、40代の官僚出身の小林鷹之だった。
存在薄の小林、支持低迷の小泉
その小林は背が高く、顔もイマドキのやり手ふう。見栄えがよくて弁も立つ、テレビは当初、彼にスポットを集中させたが、突然の出馬でいかにも知名度に欠け、争うポストがポストだけに格好がつかなかった。結局のところ、テレビ中心のメディアが世代交替の流れが出てきた、と世間にアピールし続け、選挙につきものの世論調査でも、小林・小泉の自民党の両若手が一定の支持を得ていると伝えて注目を引こうとしたが、たとえそれが正常な調査の結果だったとしても、一般人が対象の世論の動向と、実際にそれぞれの党に属して党勢拡大や選挙運動の現場を担っている党員・党友の感覚は、必ずしも同じではない。党員たちは遥かにシビアに候補者の実力を見ているし、年齢層も高いほうに偏っている。小林は時の経過とともに存在感が薄れていき、これまでもテレビで若手スターとして多く取り上げられてきた小泉が残った。
しかしその小泉も自民党の一次投票の段階でライバルの高市・石破がそれぞれ党員・党友票が100台に乗るポイントをあげたのに対して、僅か60ポイントそこそこの支持しか得られず、致命的な差をつけられた。若手もヴェテランも同じ1票の議員票では、若手が意外に多く小泉に投票したようで、微差なからトップだったものの、党員・党友票の支持の低さは挽回のしようもなく、結局9人中の3位に止まり、単独過半数を獲得した候補者が出なかったために上位2人を対象に行われるルールの決選投票には残れなかった。
その決選投票では、一次投票で党員票でも議員票でも石破をリードして、初の女性の総理総裁出現か、とも思われた高市が、地方票の比重が各都道府県連一律1票と極端に減って議員票が中心になった決選投票で、反共・反中国を明確に打ち出す姿勢が、中国に対して常に腰が引けている外務省や、それにつながる与野党に盤踞する親中議員の強い警戒心を招いたのか、頂点目前で失速。逆転勝利で石破が総裁選出馬5回目の〝最後の挑戦〟で決選に勝ち、自民党総裁の座に就き、臨時国会召集・首班指名の手続きを踏んで第102代内閣総理大臣になったわけだ。
〝お茶の間大衆性〟を持つ〝配役〟
先に決まった野田立民新代表を含めて、テレビなどが旗を振った〝世代交替〟が実現することはなく、超古物の展示会のような組み合わせになったわけだが、石破は田中角栄直系の建設官僚の2世で、初選挙の前には田中事務所で政治家の〝初歩教育〟を受けた。そもそもは保守本流の育ちで、そうした面も作用してか、反田中の棟梁だった福田赳夫子飼いの森喜朗首相のころから、安倍晋三を含めて久しく福田系が主に自民党主流として総理総裁ポストを引き継いできたことへの反発も作用して、党内野党・遠慮会釈ない反政権の毒舌タレント、といった役回りで、テレビ・ニュースだけでなく、時にはバラエティ番組にも顔を出していた。小泉進次郎が二枚目風の狂言回しとしてテレビの常連なのに対し、石破は当選12回、議員生活38年の自民党の古株にもかかわらず、本職では重鎮扱いされないかわりに、仇役風の狂言回しとしてテレビで売ってきた側面があった。尤も石破は多弁・雄弁だが政治的な経験や政策上の見識はそう深いとは思われず、所詮は口先とカッコウだけの男、トシをとった小泉進次郎、という印象もあった。
小泉の意外の失速、石破の浮上には、立民の野田代表の実現が、自民の党員・党友票にも議員投票にも影響した面があったかも知れない。野田と小泉進次郎の党首対決では、片や昭和の、というより江戸・明治以来の姿を色濃く残すドスコイおっさん。片やホストが間違って政治の世界に登場し、政治はセクシーだ、と意味不明の、しかしいかにも若者にウケそうなテレビのワイドショーの軽口ふうにしゃべる、若造りの中年男だ。これでは議論は空回り、スレ違いばかりで、どうにもならない。そこで野田に釣り合う一方で、進次郎とも通ずる、〝お茶の間大衆性〟を持つ〝配役〟として石破が浮上したのだろう。
石破政権は、こうした曲折のすえ、どこか異質・異様な感じを伴いつつ登場する。そこには、入試にたとえれば5浪して本来の同期生が卒業していった後に初志を貫徹した頑固者、仲間の声は軽視して独善・独断専行する姿に通ずる観があった。彼の過去の無数の発言には、問題の急所をついたものも、世論に大ウケしたものもあるが、概して散発的で一貫した主張に欠け、その場、そのとき限りの話題に止まるケースが多く、数が多い分だけときに整合性を欠く矛盾も目だった。
総選挙恐慌が裏目に
その石破は総理就任早々、オレ様は安倍・岸田と違って国民の支持が高いぞ、という自信を証明しようとしたのか、党内の支持勢力が弱い分だけ国民の支持の高さを見せつけようとしたのか、早期解散―総選挙を強行した。
それが裏目に出る。その背後には岸田政権時代から執拗に続いていた、自民党の末端組織や個々の議員の政治資金報告の落ち度を、共産党機関紙のアカハタが重箱の隅をつつくように掘り出し、特定の〝学者〟の〝解明〟つきで特定の大手新聞が流し、テレビが面白半分で囃し立てる、という仕組みが見えていた。それが自民党のパーティの売上金上納が高かったものに一部を褒賞金として還付し、それが選挙資金などの〝裏金〟化していたという風聞や、それが表面化して党員として現に一定の処分を受けている幹部が総選挙に際して党の公認を受けたという点を、投票直前にテレビ主体で連日さわぎたてられたために、思ってもいなかった惨敗に終わった。
自民党だけでなく、デビュー戦になった党代表を落選させた公明党。それに非公認組や保守系小会派や無所属の当選者を足しても過半数を割ったのだから、野田が呼号したように政権交替になっても不思議はない。ただし、算術計算上では確かに多数を獲得した野党勢の中には、このところ落ち目続きとはいえ共産党がいる。彼らとの同席なんかとんでもないという保守色を残す野党が複数いて、これも過半数には届かない。今秋2度目という珍事態になった国会の首班指名は、このままでは宙に浮き続きかねない状況になった。
教訓を得る最後の世代に
ここまでが本稿締めきり前の情勢だが、いまの内外情勢は中ぶらりんの政治体制を放置している余裕はない。1978=昭和53年暮れの、初めて全党員参加になった自民党総裁公選で、自信満々で再選に臨んだ福田赳夫首相が大平正芳幹事長にまさかの敗北を喫して〝天の声にもヘンな声がある〟という異様な発言を残して渋々退陣した翌79年秋の総選挙後の首班指名に対して。怨念剥き出しの指名投票に抵抗する〝40抗争〟を演じたような派閥抗争に耽ることができる状況にない。世評の憶測通り反共野党の一角が、決選投票の打開で一定の政策協定を大義に石破に投票するか、それとも棄権か無効票で自動的に石破有利に持っていくか、いずれにしても石破体制継続の姿で当面を凌ぐことにしかなるまい。筆者としては、この際野田を入閣させて挙国体制を問うて取り組みの真剣さを示す手もあると思うが、そうは運ぶまい。
尤もそれでも、石破・野田のロートル・コンビで日本の前途を深刻に捉えて一刻も早くしっかりした将来展望とそれに対処する政策体系を整え、財政再建を含めて厳格な姿勢を国民に呈して示す政治が可能だとは筆者には到底考えられない。現状ではより若い与野党の政治家を見ていても、そう感じざるを得ない。ただ彼らは、これから勉強を重ね体験を積み、今や希少になったとしても敗戦から高度成長を成し遂げた〝苦難の行軍〟を識る先人たちから、直接実態に即した教訓を得ることができる最後の世代でもある。その〝利〟を彼らが自覚して努力すれば、もはや到達点に行きついてしまい、向かうべき前途が物理的になくなった現在の政界トップ世代にくらべて、〝持ち時間〟を生かして仲間と語らって勉強会を積み重ね、遠からず将来に備えているという話も、すでに現場を離れて久しい筆者は承知しない。しかしそれが実相だったとしたら情けない。三四半世紀前の青年だった筆者としては身に迫る生活実感には生ぬるい面があって大違いとしても、現に目前に迫る〝国難〟に対する若者の奮起を臨むばかりだ。
(月刊『時評』2024年12月号掲載)